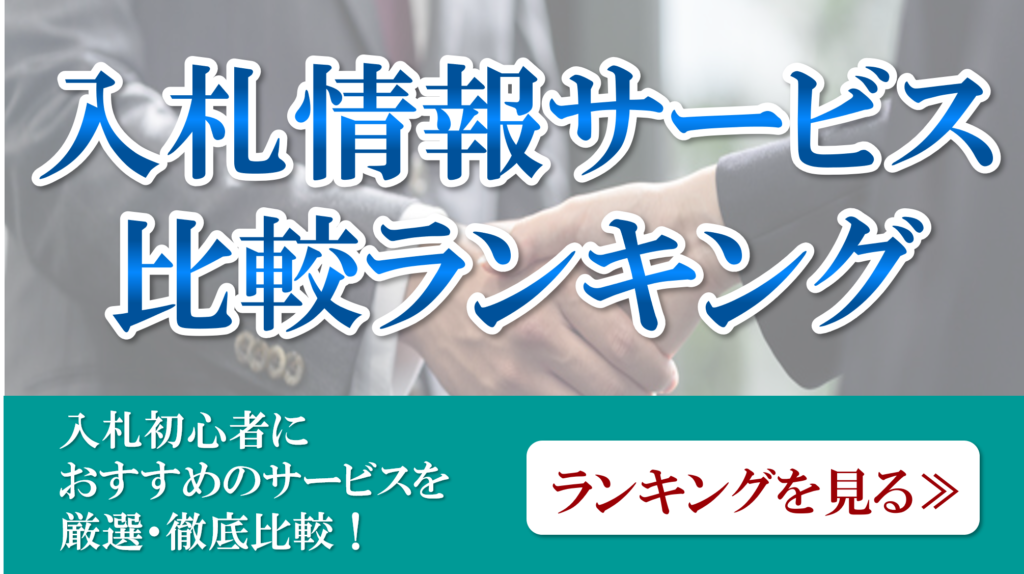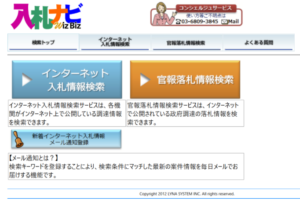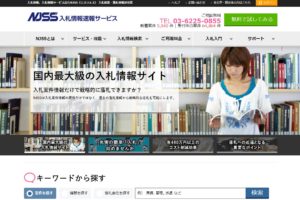入札に興味を持っている方、参加を検討されている方に向けて、公募入札とはどのような入札方式であるか解説する記事です。
入札といえば競走入札が一般的ですが、「公募入札」が開催されることもあります。
その名の通り、公募が行われる入札のことではあるものの、なぜ公募が行われるのか、どのようなメリットがるのか疑問に感じられている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回の記事では、公募入札とはどのような目的で行われるのか、メリットも含めて解説。
その後、公募入札の流れについてご紹介します。
入札に興味を持たれている方は、記事の内容を参考にして公募入札への理解を深めてください。
公募入札とは?
公募入札とはどのような入札方式か、目的やメリットを含めて見ていきましょう。
公募入札とは
公募入札とは指名競争に公募の要素を加えた入札方式のことです。
入札参加者は公募により募られ、応募してきた事業者の中から選定された複数の事業者で競走入札を行うのが公募入札の仕組み。
そのため、公募型指名競走入札と呼ばれることもあります。
以上のように公募入札とは、公募と指名競争の両方の要素を含む入札方式です。
公募入札を開催する目的とは
公募入札を開催する目的とは、入札の透明性や公正性、競走性を高めることです。
公募入札は定められた公募条件を満たしていれば、どのような事業者でも参加できます。
公募条件を満たしていれば応募できる方式であることから、一般的な指名競争入札よりも平等な入札となるでしょう。
さらに、公募条件は技術力や資格、これまでの実績であることが多いため、提供されるサービスの品質は確保されると考えられます。
公募入札を開催する目的とは、提供されるサービスの品質を確保しながら、入札の透明性・公正性・競走性を高めることです。
公募入札のメリットとは
公募入札のメリットとは、幅広い事業者が参加できることと、落札できる確率が高いことです。
公募条件さえ満たしていれば参加できる入札であるため、事業者に対しての門戸が広く、入札実績が少ない事業者に対しても入札参加の機会が与えられます。
そして、応募した事業者は審査により絞り込まれることから、入札に参加する事業者数が少なくなり落札確率が上がることもメリットです。
裏を返せば条件を満たしていなければ参加できないこと、審査を通過できない可能性があることなどデメリットにもなり得ます。
しかし、参加できる機会が与えられ、落札確率が高まることは参加する事業者にとって大きなメリットとなるでしょう。
公募入札の流れ
それでは、公募入札の流れを見ていきましょう。
- 審査会を経た後に公募が行われる
- 技術資料など必要書類を準備し応募する
- 提出書類から審査が行われる
- 審査に通過できた事業者に通知が送付される
- 指名された事業者が入札に参加する
- 開札
公募入札の流れは一般的な競争入札とそれほど変わりませんが、公募後に審査が行われ、審査通過通知を受け取る手順が加わることが大きな違いです。
もし審査に通過できたら、一般競争入札の場合と同じように入札に参加しましょう。
開札の結果、落札できたら契約となります。
以上のように、公募入札の流れで特に難しいと感じられるポイントはないはずです。
公募入札とは多くの事業者に参加機会が与えられる入札
いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでいただくことで公募入札の目的やメリットがご理解いただけたと思います。
公募入札とは、幅広い事業者に入札参加の機会が与えられるというメリットがある入札方式です。
入札情報サービスを比較し、ランキング形式で紹介しています。
比較ポイントは主に5つ、利用料金・発注機関数・情報収集方法・対象業種の広さ・サービスの評判の良さです。
入札初心者にまず必要な、豊富な『最新の案件情報』を完全無料で入手でき、自社にマッチする案件を見つけることができます。
これから入札マーケットに参入しようとしている方は、入札情報サービス比較ナビをご参照ください。