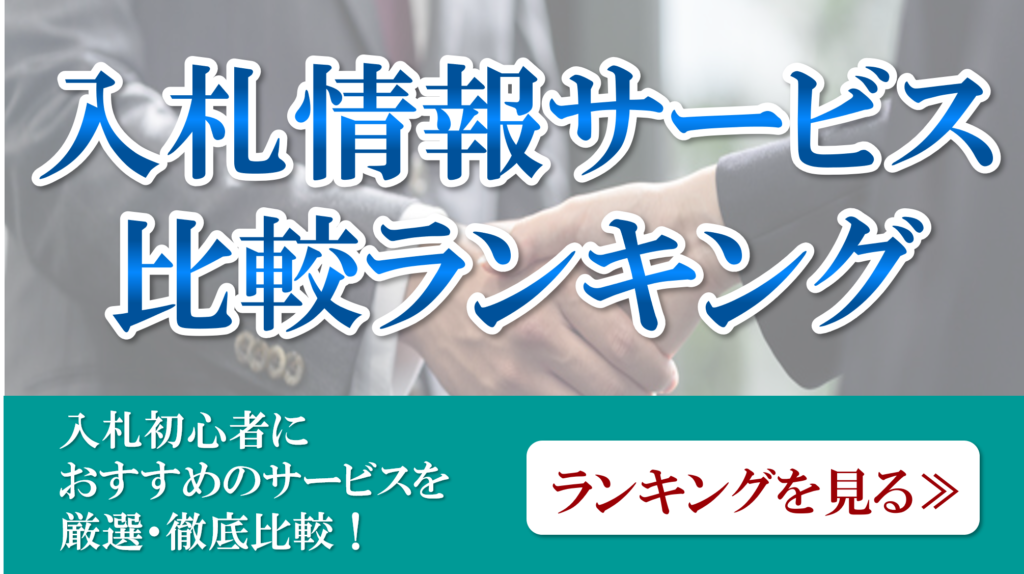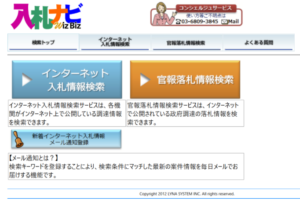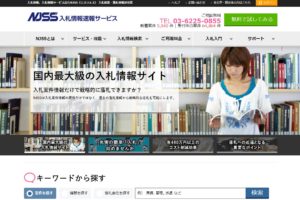入札について興味を持っている方に向けて、入札におけるダンピングについて解説する記事です。
公平性・厳正性・自由な競走などが重要視される入札では、不当な手段を用いて入札に参加することを厳しく禁じています。
入札における「ダンピング」も禁止されている行為のひとつです。
もし入札に参加して、知らずにダンピングを行えば処罰を科される可能性は高いと考えられます。
そこで今回の記事では、ダンピングの意味とともに、入札におけるダンピングと注意したい点について解説していきます。
正当に入札に参加して受注を得るために、入札において禁止事項とされているダンピングを理解しておきましょう。
Contents
ダンピングとは?
「ダンピング」とは「不当廉売」のことです。
海外企業と貿易を行うにあたって、不当な安値で商品を輸出することを「ダンピング」「不当廉売」と言います。
もし輸入した商品が自国の商品より安価で流通してしまえば、自国の産業が低迷する恐れがあることから、日本ではダンピングが禁止されています。
入札におけるダンピングについて
それでは、入札におけるダンピングについて見ていきましょう。
入札におけるダンピングとは「低価格入札」のこと
入札におけるダンピングは、「低価格入札」のことです。
案件の内容と比較して採算が合わないほどの低価格で入札を行ったり、市場の相場より著しい低価格で入札したりすることなどが該当します。
「不当に安価な商品・サービスを提供する」という概念であるダンピングは、入札においては「低価格入札」だと言えます。
入札におけるダンピングは問題視されている
入札におけるダンピングは問題視されています。
低価格で入札・落札が行われた場合、サービスや商品の品質が確保されなかったり、サービスを提供する労働者の条件が悪化したりする可能性があるためです。
入札に参加するからには落札を目指したい気持ちは誰しもが持っているでしょうが、大幅な低価格入札はダンピングとして問題になりかねません。
入札におけるダンピングへの処罰
入札においてダンピングだと判断された場合、処罰を受けることもあります。
平成26年に制定された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」では、第七条四項に「適正な工事が見込めない契約を避けるため、最低価格の設定など、必要な措置を講ずること」と[1]、ダンピング受注を禁止する旨が記載されています。
つまり、入札でダンピングを行った場合は法令違反となります。
科される処罰の内容はケースにより変わりますが[2]、法令に反すれば何らかの処罰が科されるでしょう。
低価格入札調査を拒否すると指名停止処分に
入札でダンピングだと疑われた場合に行われる調査を拒否すると、指名停止処分になることもあります。
低価格入札ではないかと疑われる事案については、外部から事業所に対し調査が行われることが多いとされます。
そして外部調査を拒否した場合は、指名停止処分となるとともに、一定期間に渡り、入札への参加が禁止されるという処罰を受ける可能性もあります。
入札への参加を続けるため、低価格入札は行わないことはもちろん、もし調査が行われるようなら拒否しないことが重要です。
ダンピングは入札においても禁止行為
いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでいただくことで入札におけるダンピングがご理解いただけたと思います。
不当な低価格入札を行うダンピングは、法令により禁止されているため行わないようにしてください。
[1]参照:e-GOV:公共工事の品質確保の促進に関する法律
[2]参照:参議院:質問主意書
入札情報サービスを比較し、ランキング形式で紹介しています。
比較ポイントは主に5つ、利用料金・発注機関数・情報収集方法・対象業種の広さ・サービスの評判の良さです。
入札初心者にまず必要な、豊富な『最新の案件情報』を完全無料で入手でき、自社にマッチする案件を見つけることができます。
これから入札マーケットに参入しようとしている方は、入札情報サービス比較ナビをご参照ください。