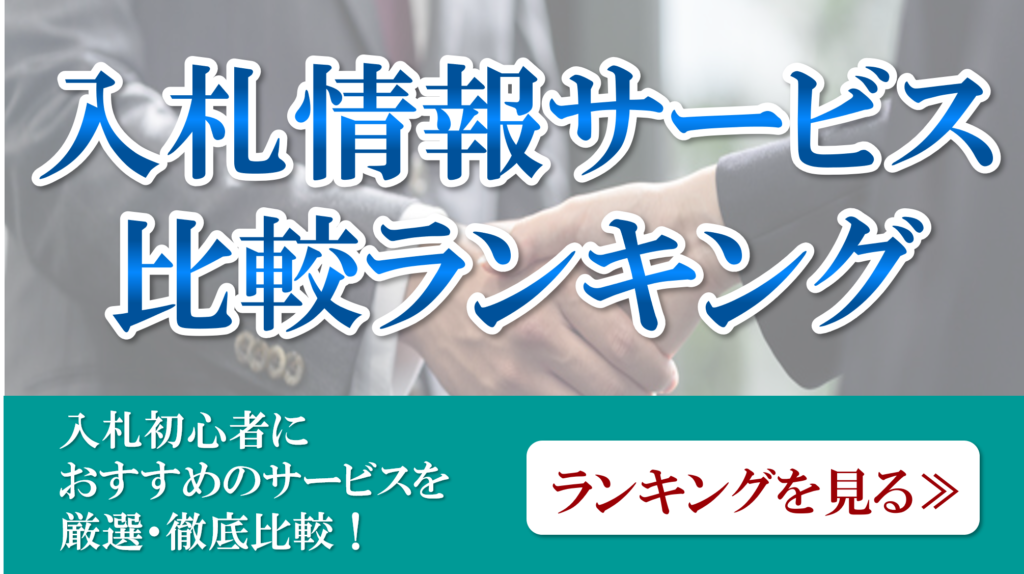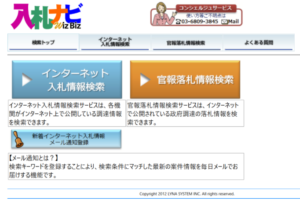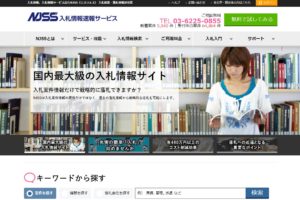今回は、入札と開札の違いについて解説します。入札に参加しようと考えている方や、入札について勉強中の方は参考にしてみてください。
入札と開札の違い
入札が指すもの
「入札」は、発注者が業務を依頼したり、物品を調達しようとする際に、契約希望者に金額などの条件を提示させ、契約者を決める一連の手続きを指します。公的機関が民間事業者の取引先を決める際や、オークションなどの場で使われます。
入札に際しては、従来、入札書や企画書等を紙ベースで提出する方式が一般的でしたが、インターネットの普及とともに、電子入札(電子調達)システムによる入札も増えてきました。
開札が指すもの
「開札」は、発注者に提出された入札書を開封する行為を指します。電子入札システムで入札した場合は、入札書の内容は暗号化されているため、それを解読可能な状態に復元(復号化)する必要があります。この復号化の作業が電子入札システムにおける開札に該当します。
開札結果は、入札参加者はもちろんのこと、入札に参加していない事業者や一般の人でも確認することができます。開札結果の情報は落札情報として、原則、官報や発注機関のサイト(調達情報に関するページ)で確認することができます。ほか、落札情報を提供している民間の入札情報サービス会社もありますので、確認してみると良いでしょう。
当サイトについて
当サイトでは、入札への参加をご検討の方向けに、お役立ていただける情報を提供しています。
また、おすすめの入札情報サービスををランキング形式で紹介しています。比較ポイントは主に5つ、利用料金・発注機関数・情報収集方法・対象業種の広さ・サービスの評判の良さです。
これから入札マーケットに参入しようとしている方は、「入札情報サービス比較ナビ」を是非ご活用ください。