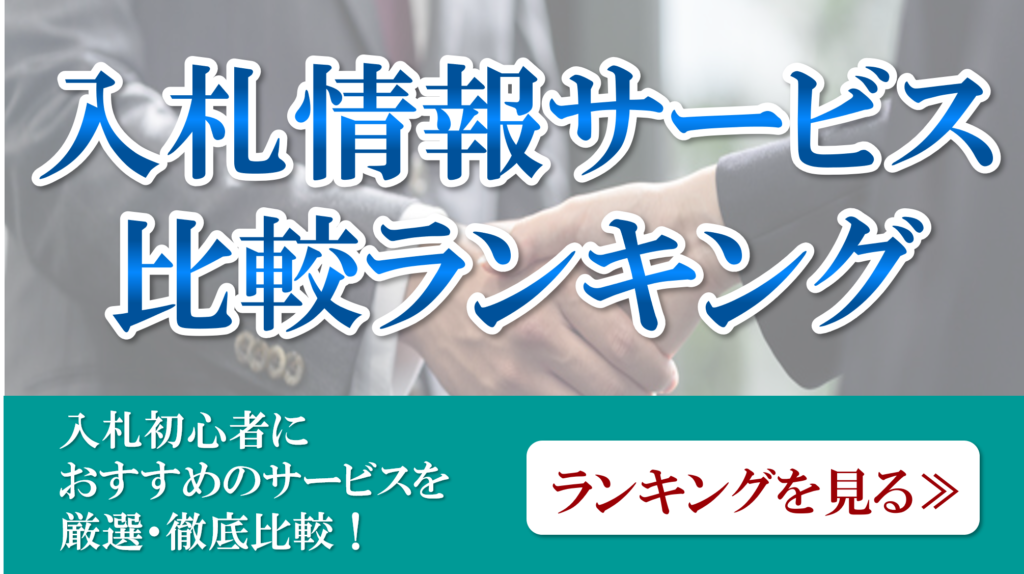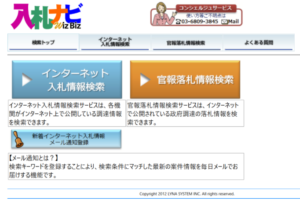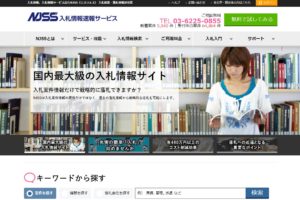入札を行う際、どうしても業務過多で手が回らない、要員が足りないなどの理由で、入札辞退をしなければならないときもあるでしょう。
そんなときにどのような手続きを踏んだらいいのか分からないという人のために、入札辞退の流れをご紹介します。
入札辞退を決めたらどのようにすればいいのか、流れを事前に把握しておくと、いざ入札辞退をしなければならなくなったときにスムーズに手続きができるでしょう。
入札辞退をするときの流れ
入札辞退をする際の流れを、順を追ってまとめてみました。
入札辞退を決定する
まず、入札を辞退することを決めます。理由については辞退する際に必要になるため、しっかりとどんな理由があって辞退をするのか整理しておきましょう。
入札を辞退するタイミングには、以下の3つがあります。
【入札辞退のタイミング】
- 仕様書取得後
- 応札後
- 落札後
応札前である仕様書取得後のタイミングでの入札辞退は、特に問題としない機関が多いようです。
機関にもよりますが、公示書や各機関のホームページ上に、辞退によるペナルティがないことが明記されています。
応札後や落札後に入札辞退を申し出ると、入札への参加が一定期間停止されてしまう場合もあるため注意が必要です。
案件ごとに対応が異なるため、入札辞退を決めたらまずは契約担当者へ一報を入れて、現段階で辞退した場合はどうなるのかを確認をするようにしましょう。
入札辞退届を作成する
入札辞退をするためには、口頭だけではなく「入札辞退届」が必要です。必要な項目は以下の通りです。
【入札辞退届に必要な項目】
- 案件名
- 入札日
- 入札辞退理由
- 住所
- 会社名
- 代表者名
- 捺印
フォーマットは各案件や発注機関によって指定があるので、確認をしておきましょう。
入札辞退をする際には、入札辞退の理由を記載する必要があります。
ただ発注機関が理由を知りたいというだけでなく、その理由を今後の案件や仕様書の書き方などに反映させて、改善に活かすこともあるようです。
入札辞退届出書を提出する
入札辞退届に必要事項を記入したら、次は案件ごとに指定されている期日までに、持参もしくは郵送にて提出します。
提出方法は案件や発注機関ごとに異なるため、公示書や仕様書に入札辞退届についての記載がないか確認しましょう。
記載がない場合には、契約担当者まで連絡をして問い合わせをしてください。
入札辞退の流れを確認してスムーズに行おう
いかがでしたでしょうか?この記事を読んでいただくことで、入札辞退の流れについてご理解いただけたと思います。
入札辞退をすることがわかったら、入札辞退届を記載し、なるべく早い段階で届け出せるように動きましょう。
当サイトでは入札情報サービスを活用できるよう、おすすめの入札サービスをランキング形式を紹介しています!良かったらチェックしてみてください。