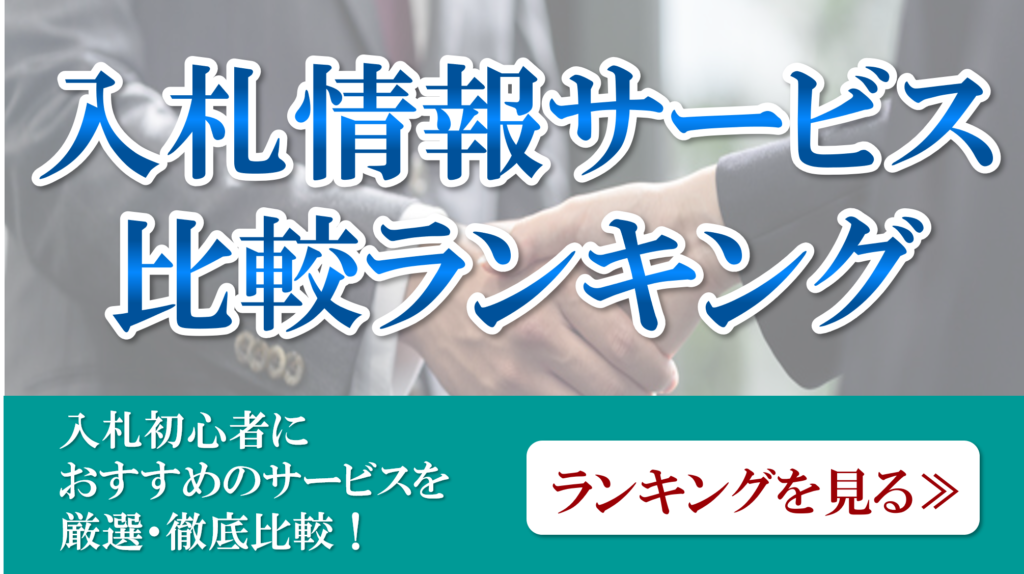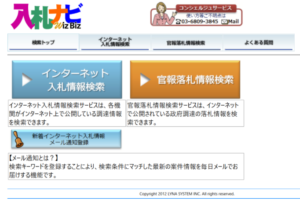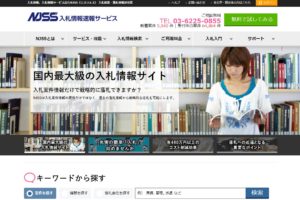「入札」と「応札」はどちらも似たような意味を持つ言葉です。実際、入札と応札は混同されがちで、一つのシーンで両方が使われることもあります。とはいえ、入札と応札には明確な違いが存在するため、正しく理解しておかなければなりません。
そこで今回は、入札と応札の違いについて解説します。入札に参加しようと考えている方や、入札について勉強中の方は参考にしてみてください。
入札と応札の違い
入札が指すもの
「入札」は、発注者が業務を依頼したり、物品を調達しようとする際に、契約希望者に金額などの条件を提示させて契約者を決める一連の手続きを指します。
公的機関が民間事業者の取引先を決める際や、オークションなどの場で使われます。
公的機関による入札では、例えば、一般競争入札や企画競争入札などがよく知られています。
応札が指すもの
「応札」は、依頼者からの求めに応じて入札に参加することを指します。具体的には、入札書を入札箱に投函するという行為が応札に値します。
なお、企画競争入札の場合は、企画書を提出することが重視されますので、この場合の応札は「応募」とも言い換えられます。
まれに、応札・応募者が1者のみで入札が行われるケースがあり、このケースは、「一者応札(一者応募)」と呼ばれます。
一者応札、一者応募となった場合は、参加者が契約の要件を満たしていれば、その参加者と依頼者との間で契約が締結されます。
当サイトについて
当サイトでは、入札への参加をご検討の方向けに、お役立ていただける情報を提供しています。
また、おすすめの入札情報サービスををランキング形式で紹介しています。比較ポイントは主に5つ、利用料金・発注機関数・情報収集方法・対象業種の広さ・サービスの評判の良さです。良かったらチェックしてみてください。