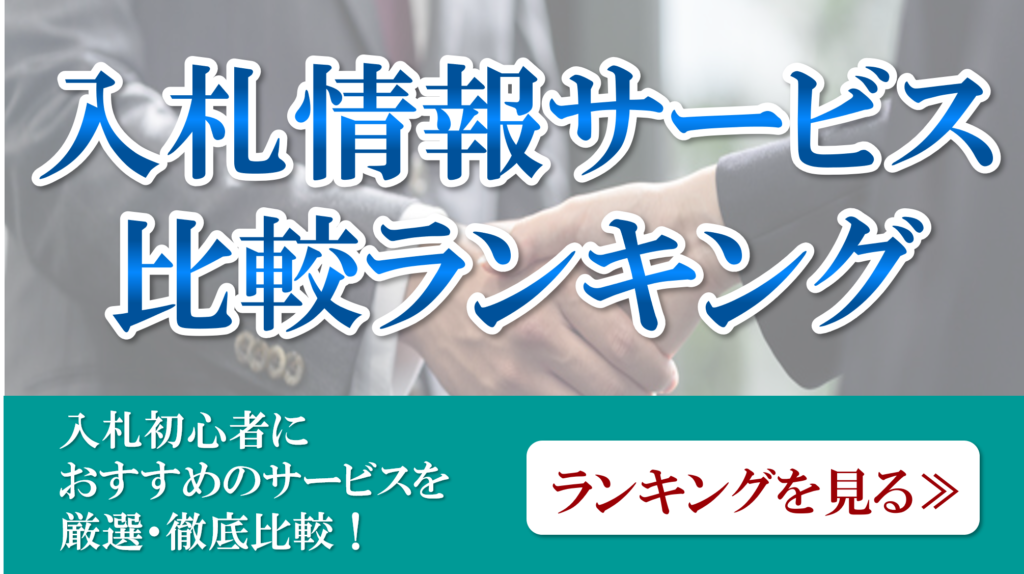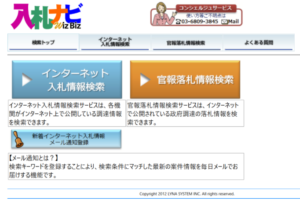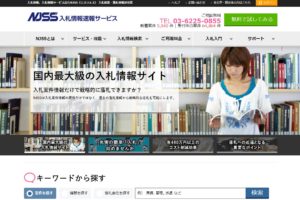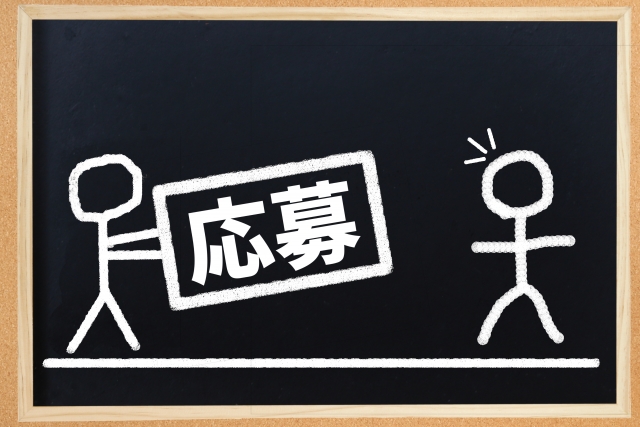
定められた資格を有する業者が参加表明書を提出し、基準により業者が選ばれ、入札を行うことができる公募型競争入札。
今回は、公募型競争入札の流れをステップごとにまとめました。
案件の検索から、参加の表明、さらに指名後の対処に関しても解説。
「公募型競争入札の流れを知りたい」という方はもちろん、「実際に入札への参加を検討しているけれど、どこから始めたらいいか分からない」という方は、ぜひ参考にされてください。
Contents
1.案件を探し参加表明書を作成・送信する
公募型競争入札は、発注者が案件に関する条件を設定し参加者を募って(公募)、その中で競争・入札を行う入札方法です。
公募型競争入札に参加するには、まず希望する条件に該当する案件を探して、入札への参加を表明しなければなりません。
案件の条件や概要は、インターネット上で公開されており、「入札情報サービスNJSS」や「入札王」などのサイトで調達することが可能です。
希望する案件を見つけたら参加表明書を作成し、必要であれば技術資料などの添付資料とともに、案件の発注者に送信・提出します。
2.発注者からの指名・非指名の審査が行われる
発注者が参加表明書を確認したら、入札参加希望書受付票というものが発行されます。
その後、発注者は、発注した案件に応募された参加表明書を確認し審査を実施。
審査に合格した参加者には、資格確認結果通知書が送られ、指名の通達が行われます。
この時、審査に合格できなかった場合には、その参加者宛に非指名の通達が行われる仕組みです。
3.指名された業者は入札書を提出する
発注者から指名された業者は、資格確認結果通知書を受け取り、入札を確認します。
その後、入札書に金額を入力して提出。
この時、入札を辞退する場合は、発注者に向けて辞退届を提出します。
4.発注者による開札・入札結果通知が行われる
提出した入札書は、発注者により開札され、入札審査が実施されます。
発注者からは入札締切通知書が発行され、入札状況と結果の登録を実施。
応募者は、入札結果の決定通知書を持って入札の確認を行います。
公募型競争入札流れを把握してスムーズな取引を
いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでいただくことで公募型競争入札の流れがご理解いただけたと思います。
全体の流れをステップごとで理解し、把握しておくことで、いざというときにスムーズな取引が可能になります。
希望する案件の獲得の際に、ぜひお役立てください。