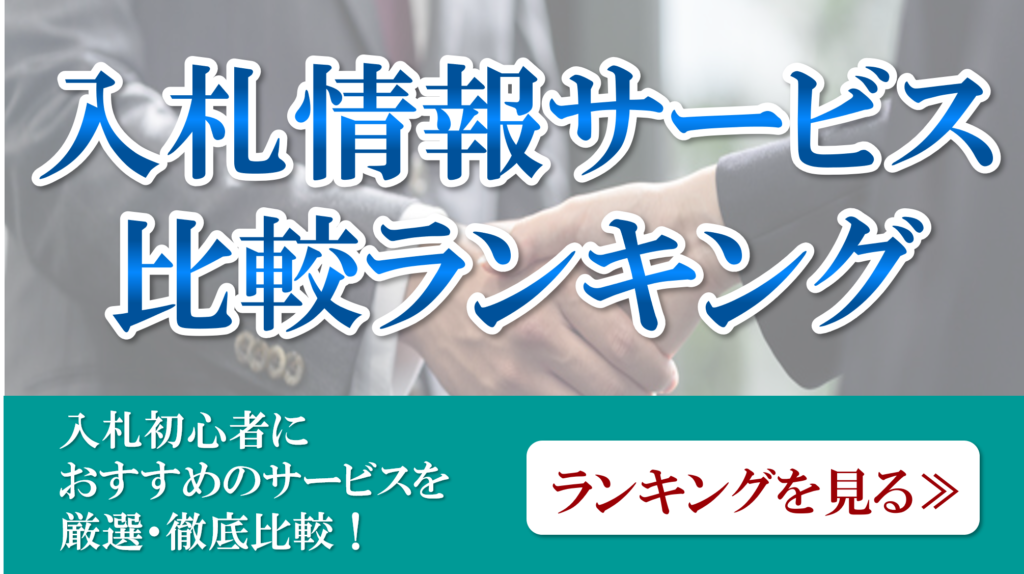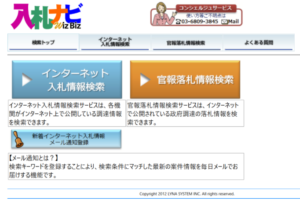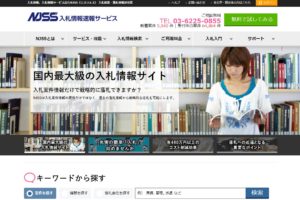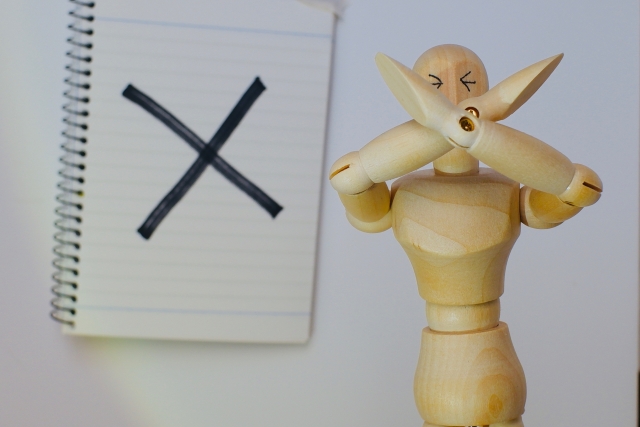
入札に関心を持ち、参加を検討されている方に向けて入札での禁止事項を解説する記事です。
入札では「公正で自由な競争」を重要視しており、入札においてすべての事業所が公正で自由な競争に参加できるよう禁止事項が定められています。
また、地方公共団体との契約により遂行される事業は、国税から支払われることから公正性と厳正性は特に重視されています。
禁止事項に抵触する行為を行った場合、刑法の定めにより懲役や罰金が科せられることもあるでしょう。
そのため、入札への参加を検討するにあたり、禁止事項を正しく知っておくことは必須です。
今回の記事では、入札における禁止事項や注意点について解説していくので、入札に参加する前に禁止行為を確認しておいてください。
Contents
入札における禁止事項とは
入札における禁止事項は次のとおりです。
発注予定者・最低入札価格を予め決定すること
入札において発注予定者や最低入札価格をあらかじめ決定することは禁止されています。
入札予定者や最低入札価格があらかじめ決められている入札は公正とは言えず、自由な競争を阻害する行為であり、独占禁止法第三条における「不当な取引制限の禁止」に該当する違反行為に該当するためです。
発注する側への禁止事項ではありますが、「入札談合」と呼ばれる対象の行為は、公正取引委員会では最も悪質な独占禁止法違反行為だとしています。
発注予定者や最低入札価格をあらかじめ決定して、不公正な取引を行うことは入札禁止事項です。
制限や不公正が生じる活動や取引方法
入札では競争において制限や不公正が生じる活動・取引方法など全般を禁止事項としています。
前項で解説した入札談合も制限や不公正が生じる取引方法のひとつですが、その他、次のような例も入札での禁止行為に該当する行為です。
【制限や不公正が生じる活動・取引方法の例】
- 取引・競争が行われる分野での実質的制限
- 事業者団体側から事業者数に制限を設ける行為
- 構成事業者の機能や活動を不当に制限する行為
- 事業者に不公正な取引を強要すること
- 事業者が不公正な取引を行うこと
たとえば、受注予定者の受注意欲や営業活動実績などの情報を、事業者団体が収集したり、事業者間で共有したりすることも、公正な取引に反するとして違反行為だと判断されたことがありました。
取引や競走、活動に関して制限や不公正が行われることは、入札談合に限らずすべて禁止とされています。
入札における禁止事項についての注意点
禁止事項行為を必ず行わないようにすることが、入札における最大の注意点です。
もし禁止行為を行った場合、「不当な取引制限」に該当し独占禁止法違反として処罰を受ける可能性があるだけでなく、刑法の「談合罪」や「収賄罪」に抵触することも考えられます。
もし禁止事項行為を行った場合、懲役や罰金を科せられたり、公正取引委員会による排除措置が行われたり、課徴金が科せられたりすることもあります。
また、損害賠償を請求される可能性もあるでしょう。
入札における禁止事項は必ず事前に確認し、行わないように細心の注意を払わなければなりません。
公正・自由な入札は禁止事項行為を行わないことで実現する
いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでいただくことで、入札における禁止事項がご理解いただけたと思います。
公正で自由な入札が行われるためには、参加するすべての事業者が禁止事項行為を行わないようにしなければなりません。
入札情報サービスを比較し、ランキング形式で紹介しています。
比較ポイントは主に5つ、利用料金・発注機関数・情報収集方法・対象業種の広さ・サービスの評判の良さです。
入札初心者にまず必要な、豊富な『最新の案件情報』を完全無料で入手でき、自社にマッチする案件を見つけることができます。
これから入札マーケットに参入しようとしている方は、入札情報サービス比較ナビをご参照ください。