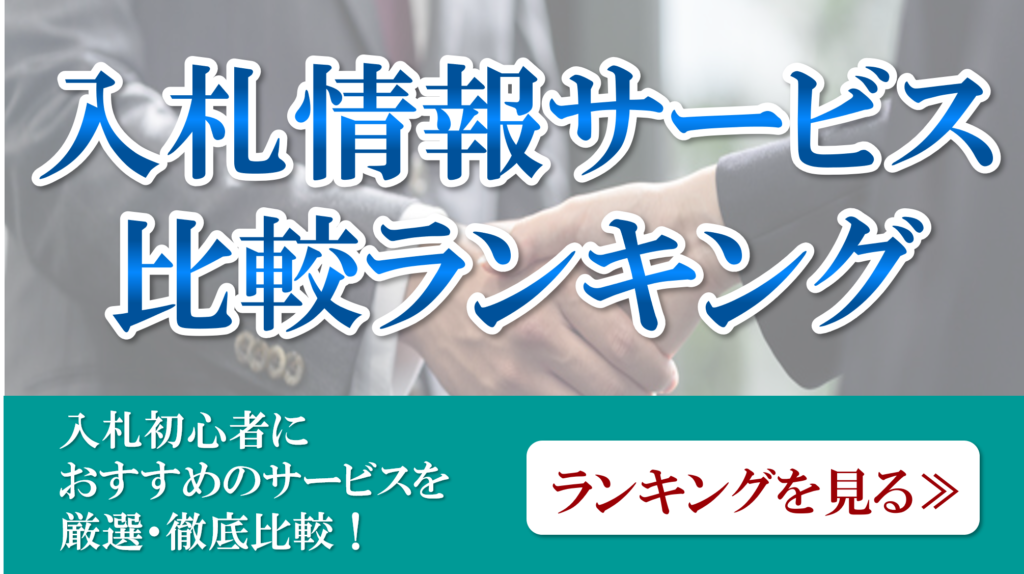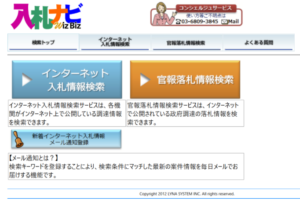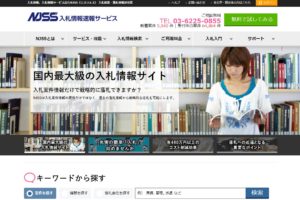入札に関心を持っている方に向けて、随意契約とは何か、種類やメリット・デメリットについて解説します。
入札は一般的に入札手続きを経て、複数の事業者が競走をして落札者が決定されますが、入札をせず契約を締結させる契約方式が「随意契約」です。
随意契約には主に3つの種類があり、実施される条件などが異なります。
今回の記事では、随意契約にはどのような種類があるのか特徴を解説した後に、随意契約のメリット・デメリット、通常の入札とどちらを選ぶべきかについて解説します。
入札に関して情報を集めたいと思われている方は、入札手続きなしで契約が締結される随意契約についてもぜひ知識を深めてください。
Contents
入札の随意契約とは何か
入札の「随意契約」とは、入札をせず契約する事業者を決定することです。
多数の事業者が公正な競走を行うこととする入札において例外的な契約方法。
随意契約には次の4種類があります。
少額随意契約
「少額随意契約」とは、入札手続きを行わない契約方式のことです。
入札手続きを簡略化するために行われ、事前に契約相手となる事業者を2~3社程度厳選した後に、3社から見積もりを受け取って最も安い価格を提示した事業者と契約を行います。
見積もり合わせを行わず特定の事業者と契約を締結するケースもありますが、入札手続きを行わず最安値を提示した事業者と契約をするのが少額随意契約です。
特命随意契約
「特命随意契約」とは、国が競走をさせることなく特定事業者と契約を結ぶ入札方式のことです。
発注者側の都合や事業者側との長期的な付き合いを理由として実施されることがほとんどで、代表的な随意契約の形。
発注者側の都合により、国が事業者に競走をさせず、信頼性の高い特定事業者と契約を結ぶ随意契約を特命随意契約と呼びます。
不落随意契約
「不落随意契約」とは、落札者や入札参加者が不在であった場合に実施される契約方式のことです。
また、落札者が契約締結を拒否した場合も不落随意契約となります。
落札者が不在であったものの契約をすぐに締結しなければならない場合に実施されます。
以上のように不落随意契約は入札手続きを実施したものの、入札において契約先の事業者が不在であった場合に行われる随意契約です。
随意契約を結ぶメリット・デメリット
随意契約を締結するメリットとデメリットは次のとおりです。
【随意契約のメリット】
- 工事などの品質が高くなる傾向にある
- 落札が確実となる
【随意契約のデメリット】
- 工事金額が高額になる恐れがある
- 随意契約先の事業者として選ばれにくい
特命随意契約では発注側が事業者を吟味するため、品質の高い業務が期待できるものの、競走相手がいないため価格が高くなる可能性もあります。
また、随意契約全般においては契約先の事業者として選ばれれば落札は確実となりますが、契約先事業者として選ばれることは簡単ではありません。
随意契約と入札の違いは?どう選べばよいか
随意契約と入札の違いは、契約において入札手続きが行われるかどうかです。
どちらを選ぶべきかは、確実性や迅速性を重視するなら随意契約を、安全性を重視するなら一般入札を選ぶべきでしょう。
入札手続きが行われない随意契約は、手続きを省略することで迅速性が増し、契約相手を選べることから確実性もあります。
ただし、法令上は競走が伴う一般入札のほうが推奨されており、公平性を欠くことから社会的問題になりやすいのが随意契約であることから、安全性で選ぶなら一般入札をおすすめします。
随意契約は入札手続きを行わない契約方式
いかがでしたでしょうか?
この記事を読んでいただくことで随意契約についてご理解いただけたと思います。
随意契約とは入札手続きを経ず、事業者と契約を締結する契約方式です。
入札情報サービスを比較し、ランキング形式で紹介しています。
比較ポイントは主に5つ、利用料金・発注機関数・情報収集方法・対象業種の広さ・サービスの評判の良さです。
入札初心者にまず必要な、豊富な『最新の案件情報』を完全無料で入手でき、自社にマッチする案件を見つけることができます。
これから入札マーケットに参入しようとしている方は、入札情報サービス比較ナビをご参照ください。